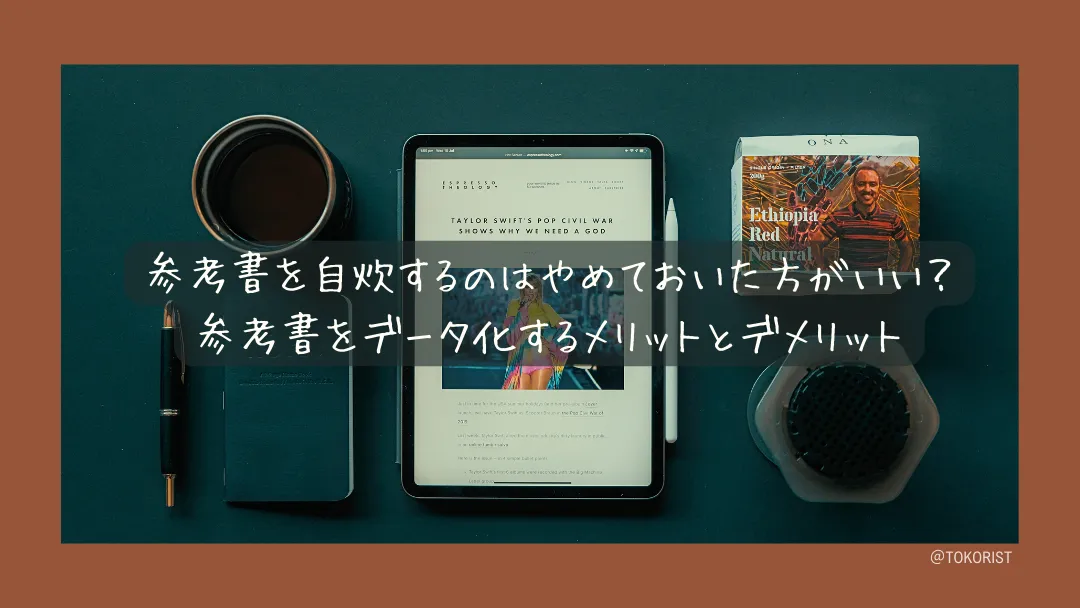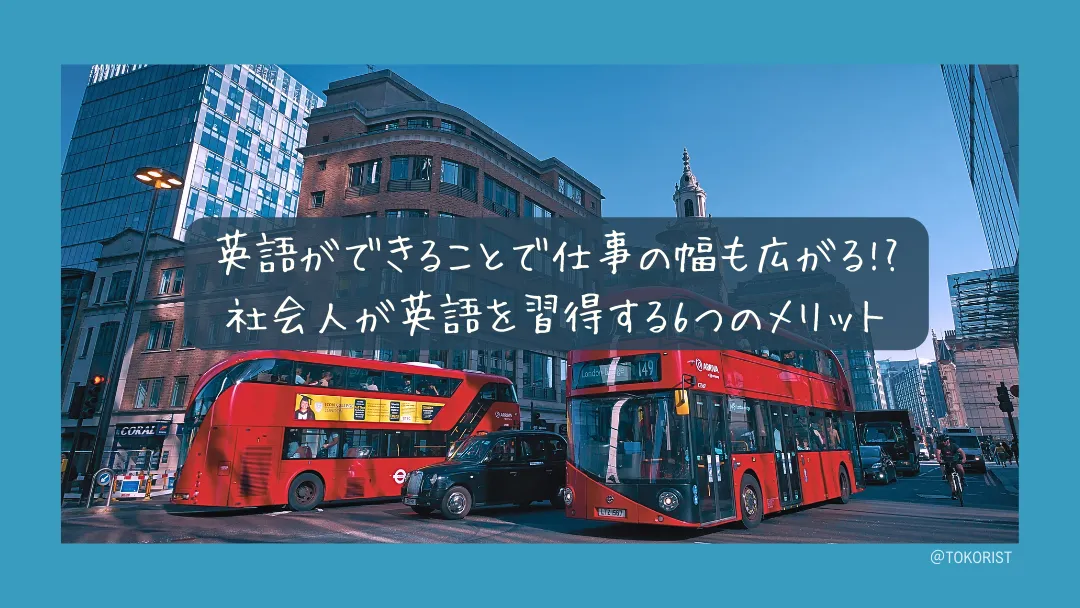参考書をデータ化する、いわゆる「自炊」は、学生や社会人にとって魅力的な方法です。紙の参考書をデジタル化することで、持ち運びが便利になり、収納スペースも節約できるなど多くの利点があります。
一方で、デジタル化することで生じるデメリットもあります。
今回は、参考書をデータ化するメリットとデメリットについて詳しく見ていきます!
メリット
1.
持ち運びが便利
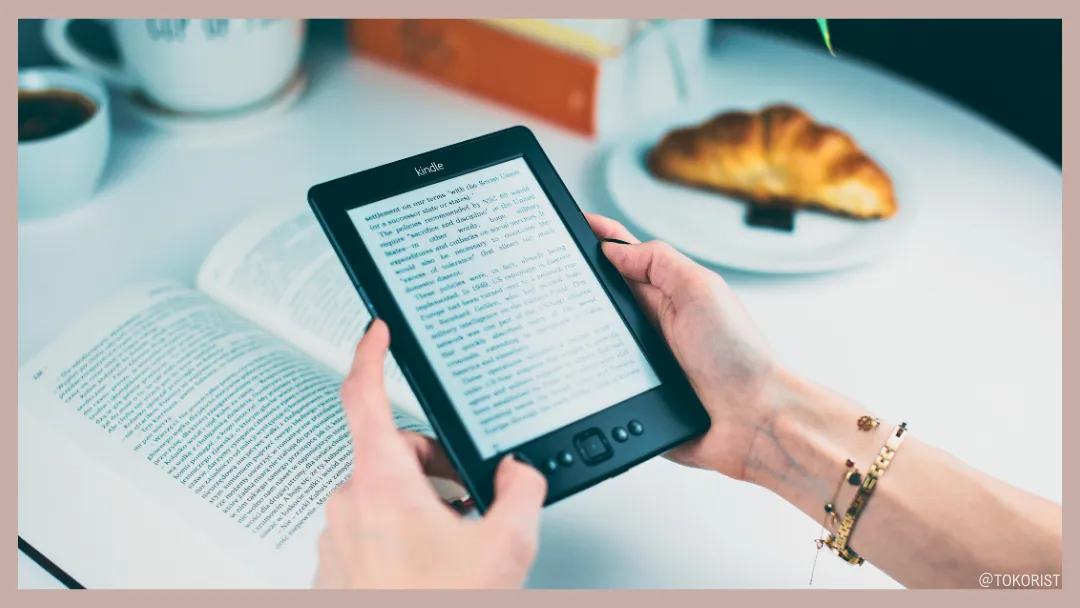
参考書をデジタル化することで、スマホやタブレット、パソコンでいつでも閲覧できるため、どこでも勉強ができます。重い参考書を持ち歩く必要がなくなるのは大きな利点です。
スマホやタブレットを開けば、どこでも勉強できるのは効率的ですきま時間の勉強にもピッタリです!大きなバッグを持ち歩きたくない日でも、荷物を重くしたくない日でも問題なく勉強することができます。
2.
ツールが使える
デジタル化することで、特定のキーワードを検索する機能を使うことができます。
これにより、必要な情報を素早く見つけ出すことができ、効率的に勉強を進めることができます。また、重要な箇所をマークしたり、メモを追加することも容易です。
試験の問題集のように、終わったら手放す予定の参考書に書き込みを加えると、売る際に値段が下がり値段がつかないことも。とはいえ、書き込みをしないで勉強を進めるのは、気を使って集中できない!
そんな方は、自炊して参考書をデジタル化するか、デジタル版を購入するのがオススメです。デジタルなら、気兼ねなく書き込みすることができ、消しゴム機能も使えて勉強がはかどります。
3.
スペースの節約

紙の参考書を保管するにはスペースが必要です。デジタル化することで、物理的なスペースを節約し、書棚や部屋を整理整頓することができます。
限られたスペースを有効に活用できるため、整理整頓された学習環境をつくれます。
4.
環境にやさしい
デジタル化することで、紙の消費を減らし、環境負荷を軽減することができます。特に、大量の参考書を使用する場合は、この点が大きなメリットとなります。
デジタル版を購入するのが最も環境にやさしい選択ですが、デジタル版だけでは勉強がちゃんとできるか不安という方も中にはいらっしゃるでしょう。
その場合、中古の参考書を購入し自炊するのが良いかもしれません。中古品なら気兼ねなくデジタル化でき、なおかつ、デジタルの参考書で勉強がはかどらなかった時のために、紙の参考書を保管することができます。
5.
バックアップが取れる
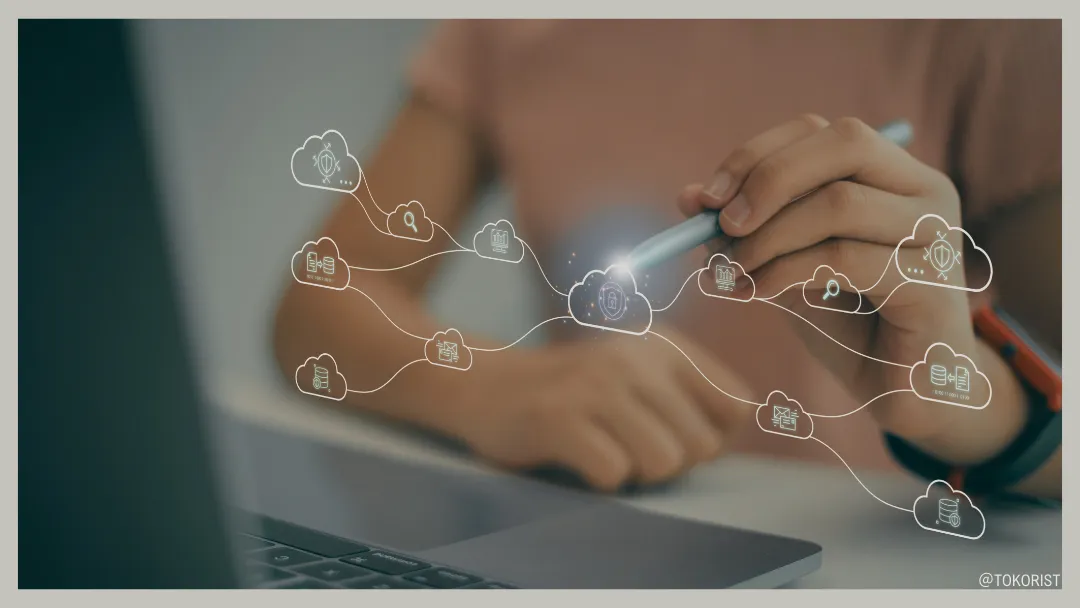
デジタル化された参考書は、クラウドサービスなどを利用してバックアップを取ることができます。
これにより、紛失や破損のリスクを軽減し、重要な資料を安全に保管することができます。
また、水濡れや書き込みの誤字など、汚れを気にせずキレイな状態のまま勉強できます。劣化や破損の心配がなく、安心してデータを管理でき非常に便利です!
デメリット
1.
データの破損や紛失のリスク

アナログの汚れや破損の心配がない一方で、データのウイルスやハードウェアの故障などによる破損や紛失のリスクがあります。適宜、データのバックアップを取っておくことやデータの安全性に注意が必要です。
2.
読みづらさ

紙の本に比べて、デジタルデバイスでの長時間の読書は目に負担がかかります。特に長時間勉強する場合、紙の参考書の方が読みやすいと言われています。
中には、デジタルで勉強するのは向いていないと感じ、参考書をデジタル化するのは効率的な勉強方法だと思わない方もいらっしゃるかもしれません。
スマホやタブレットの「読書モード」機能を使用して、少しでも目の負担を軽減させて読むのがおすすめです。また「就寝前はデジタルで勉強しない」といったマイルールを決めて勉強するのも良いかもしれません。
3.
スキャンの手間
参考書を自炊するには、スキャナーで1ページ1ページ、スキャンする必要があります。この作業は非常に手間がかかり、時間も労力も必要です。そのため、効率的にデジタル化するための方法を見つけることが課題となります。
4.
著作権の問題
参考書をデジタル化することは、著作権法に抵触する可能性があります。特に、他人に配布したり共有する行為は違法となるため、注意が必要です!
5.
デバイス依存

デジタル化された参考書を閲覧するためには、スマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスが必要です。
これらのデバイスが故障したり、バッテリーが切れると参考書が利用できなくなります。そのため、予備のデバイスや充電器の準備が必要です。
また、図書館やカフェなど一部では勉強スペースが制限されてしまうことにも注意が必要です!
まとめ
参考書をデータ化することには多くのメリットがありますが、同時にデメリットも存在します。自分の勉強スタイルやライフスタイルに合わせて、デジタル化するかどうかを慎重に判断することが重要です。
今回ご紹介したポイントを参考に、自分に最適な勉強スタイルを探してみてください!